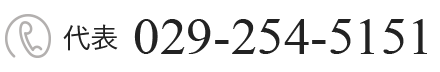血液内科

01血液内科とは
血液内科がどういう専門の分野か,正確にはご存知ない患者さんも少なくないと思います。健康診断で行う血液検査の結果に何か異常があると血液内科に紹介される,と間違った回答をする医学生もいますので,分かりにくいのは無理もないことです。
血液内科医が診療にあたる血液の病気というのは,血液の細胞(血球)が減ったり増えたりする病気,あるいはこれらが「がん」になる病気,および,血が止まりにくくなる病気などが主体です。具体的には,以下のような病気があります。
病気について知る
- いろいろな貧血(貧血というのは,血液の中の赤い成分が薄くなる病気のことです)
- 血小板減少症
- 白血病
- 骨髄異形成症候群
- 骨髄増殖性腫瘍(血球が増える病気)
- 悪性リンパ腫
- 骨髄腫
- 血友病
症状について知る
こうした病気を持つ患者さんは,健康診断で気づかれたり,血圧や糖尿病などで通院中にかかりつけ医の先生が発見して下さったりすることもあります。一方で,急激に強い症状がでて短い間に進んで紹介される場合もあり,発見の契機はさまざまです。
一般に重い病気と考えられがちで,紹介された時点で患者さんは悪い病気ではないかと大変心配なさっていることもあります。確かに白血病などは命に関わることも少なくありませんが,一方で治療の進歩が大変に著しい分野でもあります。20年前と現在とでは,同じ病気と診断された場合でも,治療後の見通しはずいぶん違います。治る,あるいは治らないまでも元気で長い間健康人と同じように過ごせる患者さんがどんどん増えています。
一方で,治療には長い時間がかかることも少なくありません。私たち血液内科医は,患者さんの良きパートナーとして,個々の患者さんにとって最良の結果が得られることを目指します。
02水戸済生会総合病院・血液内科のご紹介
水戸済生会総合病院では,一時期は新潟大学から派遣された血液専門医2名体制で多数の血液患者の入院診療を行なっていましたが,2016年頃から人員減の影響で入院診療を絞ってきました。その後2022年度から筑波大学血液内科に所属する非常勤の専門医が1名そして2名へと増え,2024年度はこれらの2名が常勤になりました。10月からはさらに筑波大学血液内科出身の専門医1名が増え,以前から長いあいだ血液内科診療に携わってきた長山礼三医師(嘱託医師)を含め総勢で4名になりました。このうち千葉滋医師は筑波大学医学医療系教授と水戸済生会総合病院最高技術顧問を兼ね,小川晋一医師および清木祐介医師はそれぞれ血液内科主任部長および部長を務めます。
千葉医師は本年3月まで筑波大学血液内科教授として16年にわたり大学病院における造血幹細胞移植をはじめとする血液疾患医療,および研究を率いてきました。小川医師は筑波大学で専門研修後,2015年から本年までJAとりで総合医療センターにおいて血液内科で診療にあたってきました。清木医師は,筑波大学大学院で学位を取得後病院助教として附属病院で血液専門診療を経験しました。これら多くの経験を活かし,また以下に述べる4つの連携を通じて,茨城県央〜県北部に居住する患者さんを中心に質の良い医療を提供したいと思います。さらにまた,茨城県全体の血液疾患診療の発展に貢献できればと思います。

スタッフの連携10床の無菌病床を活用し,また多職種医療スタッフの連携によって,
化学療法と造血幹細胞移植療法を積極的に展開します
水戸済生会総合病院では本年8月,新棟3階病棟の一部を改修し10床(個室2室,4床室2室)の無菌病床を開設しました。無菌室前の廊下にもヘパフィルターを設置して層流を実現しました。これにより,患者さんがより円滑なリハビリテーションを行うことができると期待されます。早速9月から化学療法後の高度の白血球減少症の患者さんが利用しています。順次,自家移植と血縁者間同種移植を行って実績を積み,非血縁者からの骨髄・末梢血幹細胞移植施設認定,移植施設認定を受けられるようにしていきます。これによって県内で不足している移植実施能力の増加に貢献したいと思います。なお,無菌病室は無菌加算を取得することで,当院の経営にもいくばくかの貢献ができればよいとも思います。


総合内科との連携総合内科との連携により総合知を結集し,
病病連携〜病診連携を推進するとともに,若手医師教育にも尽力します
当院では以前から循環器内科専門医で主任部長である千葉義郎医師を中心に,総合内科が活発に診療と研修医教育に取り組んできました。この取り組みは,研修医の応募が定員の300%に達するなど支持を得ることにも貢献してきました。本年4月からは,血液内科医2名(10月から3名)と膠原病内科医2名がこのチームに加わり,大きな総合内科チームとして患者さんの診療にあたっています。この体制は複数の専門家が毎日一同に会して患者情報を共有したり,知識や経験を補い合ったりする上で非常に有効に機能しています。また,病病連携や病診連携の円滑な運営を後押ししています。一方,研修医も総合内科ローテーションによってより幅広く,また深い知識や経験を積むことができ,より良い教育を受ける場になっていると思います。

病院間の連携茨城県立こども病院との連携により,血液疾患治療センターを拡充します
成人(思春期以降)血液疾患の診療にあたる血液内科医と,小児血液疾患の診療にあたる小児科医(血液・腫瘍専門)は,専門資格として共通の「血液専門医」(日本血液学会認定)を取得します。両者は内科・小児科の枠を超えて,従来から学術活動の場で,あるいは教育の場で,連携してきました。
実は,水戸済生会総合病院は茨城県立こども病院と一つ屋根の建物になっています。茨城県立こども病院は,従来から県内で行われる造血幹細胞移植の過半数を担当してきましたので,多くの経験とノウハウが蓄積されています。今後は,県立こども病院の小児血液内科の先生方とも協同し,双方にとってより良い方向に進めるように努力してまいります。
水戸済生会総合病院の中に組織化される予定の「血液疾患治療センター」では,県立こども病院と協同できる活動を広げ,センターとしての実績を積んでいきたいと思います。

県内の連携茨城県内の血液内科施設との連携により,
県央〜県北地域の血液疾患患者さんにこれまで以上に質の良い医療を提供し,
また県全体の血液疾患診療の拡充に貢献します
茨城県の血液内科診療施設はこれまでも筑波大学血液内科を中心に,共同してマニュアルを作成し毎年更新するなど,連携を発展させてきました。筑波大学血液内科は千葉医師の後任として坂田麻実子教授が着任しています。今後は坂田教授のリーダーシップのもとで,こうした連携が益々進化するものと期待されます。水戸済生会総合病院は,そうした連携の中で,県央〜県北地域の血液疾患患者さんにこれまで以上に質の良い医療を提供し,また県全体の血液疾患診療の拡充に貢献していきたいと思います。


症例数(令和5年度)
新規患者
| 疾患 | 患者数 |
| 急性骨髄白血病 | 1 |
| 骨髄異形成症候群 | 1 |
| 慢性リンパ性白血病 | 1 |
| 悪性リンパ腫 | 9 |
| 原発性マクログロブリン血症 | 1 |
| 原発性ALアミロイドーシス | 1 |
| 突発性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| 意義不明の単クローン性γグロブリン血症 | 1 |
| 総数 | 17 |
担当医師紹介
-
 顧問長山 礼三
顧問長山 礼三出身大学(卒業年)
- 新潟大学(昭和52年)
認定資格等
- 日本血液学会 血液専門医・指導医
- 日本内科学会 指導医
- 日本臨床腫瘍学会 暫定指導医
- 日本環境感染症学会 ICD